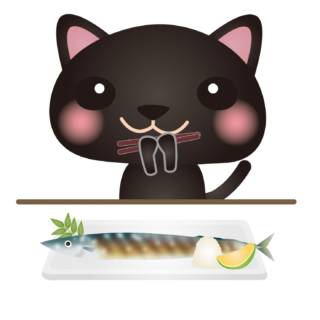夏といえば、風物詩である流しそうめんが食べたくなりますよね。暑い夏の太陽の下で食べる流しそうめんは、他では味わえない美味しさと涼しさを感じます。
そんな流しそうめんにとって、流すための竹は必需品。竹は用意するだけでも一苦労です。
しかし、竹は放っておくと、丸まったり変色してしまうことも。せっかく手に入れた竹も、使いものにならなくては意味がありません。
また、来シーズンも同じ竹を使いたいけど、使い捨てで捨てたほうがいいと言う声もあります。
そこで今回は、そんな竹の正しい保存方法や、来シーズンにも使って大丈夫なのかなどをご紹介したいと思います。
スポンサーリンク
読みたい場所へジャンプ!
流しそうめんの竹を実際に使うまで保存する方法

流しそうめんの竹を取ってくるのは、流しそうめんをする当日、もしくは前日がいいとされています。
早くとってきすぎると、カビがはえやすくなってしまうからなんですね。
竹にはもともと中に水分が含まれています。その水分が竹を切り取ることで空気に触れ、カビが発生してしまうんです。
なので、流しそうめんに使う竹は、なるべく取りたての竹が好まれます。
早くとってしまった竹は、使うギリギリまで割らずに置いておくとカビがはえてくるのを遅らせることができます。
また、新しい竹は古い竹よりも水分が多いです。竹を取ってくる際は、なるべく2年目以降の竹を取るようにします。
当日に竹を割り、そのままだと衛生的によくないので、無水アルコールで消毒してから流しそうめんをしましょう。
流しそうめんの竹が丸まる原因と対策は?

切ってきた竹が丸まってしまうのは、竹の中にもともとある水分が急激に乾燥したことで縮んでしまい、その結果丸まってしまいます。
そのため、天日干しなどをしておくと、丸まりやすくなります。先ほどご紹介したのと同じように、こちらも使うときまで割らないで保管しておくと、丸まりにくいです。
竹を保管するのに乾燥は大事ですが、急激な乾燥や乾燥のしすぎは逆に丸まる原因になりますので、天日干しはせず、風通しのいい場所に陰干ししておくようにしましょう。
スポンサーリンク
流しそうめんの竹の保存で終わった後のカビが生えない保存法と洗い方

流しそうめんに使った竹は、そのままにしておくとすぐにカビがはえてきてしまいます。
また、ホコリをかぶらないようにとカバーなどをしておくと、湿気がたまり、カビがはえてきやすくなってしまいます。
流しそうめんをし終えたら、まず熱湯をかけて消毒をします。そのあとできるだけはやく乾燥させて無水アルコールを使って、竹をもういちど消毒しましょう。
湿気の多い場所に置いておくとカビがはえてしまうので、風通しのいい場所での保管を徹底してください。
流しそうめんの竹は保存して次のシーズンも使ってもいい?

竹はご紹介したとおり、乾燥しやすくカビがはえやすいので、保存の仕方が難しいものです。
1シーズンで何度も使うことすらたいへんで、使い捨てだと考える人も。使うたびにしっかりと乾燥させ、無水アルコールで消毒をして風とおしのいい場所での保管が必須です。
このことを守っていても、カビがはえてしまうこともあります。できるだけ流しそうめんの竹は1年で捨てるようにしたほうがいいです。
どうしても次のシーズンも使いたい場合は、保存に気をつけて、使うときにカビがはえていないかなど、しっかりと確認してから使いましょう。
まとめ
竹はとてもデリケートで、水分が多いとカビがはえ、乾燥しすぎると丸まってしまいます。
特に1年目の新竹は古い竹に比べて水分が多いので、カビがはえやすく丸まりやすいです。
流しそうめんには、2年目以降の竹を使いましょう。取ってくるのは、できるだけ流しそうめんの当日か前日に取ってくることで、カビがはえたり丸まるのを遅らせることができます。
はやく取ってきてしまっても、竹を割るのは当日まで我慢です。使用後は洗い流してしっかりと乾燥させ、無水アルコールで消毒をして風通しのいい場所に保管しておきます。
きちんとした保管方法を守っていれば1シーズンは使うことができますが、来シーズンまでは難しいもの。
まだ使う前の状態でも、何度か使った後でも、次のシーズンのときでも、竹にカビがはえてしまっていたらもったいないですが捨てるようにしましょう。
おいしい流しそうめんを食べるためにも、清潔な竹を使ってください。
スポンサーリンク